| |
|
|
|
|
| |
|
|
 |
アルファ・ベータT(・デルタ・ティー)細胞とは
|
|
| |
|
|
αβT細胞療法とは,採血により,末梢血液中に含まれるリンパ球を取り出し,約2週間,抗CD3抗体とインターロイキン-2(IL-2)とを用いて培養し,活性化・増殖させたT細胞を体内に戻す治療法です。
この治療法は一般に活性化自己リンパ球療法とよばれている免疫細胞療法の一種です。
この治療で使用されている抗CD3抗体とは,T細胞の細胞表面に存在する目印ともなるCD3分子を認識する物質で,抗CD3抗体によりCD3分子が刺激を受けるとT細胞が活性化します。
そこで,この方法はCAT(CD3-activated Tcells)療法とも呼ばれています。
一方,サイトカインの一種インターロイキン-2(IL-2)を与えることで,インターロイキン-2はT細胞やNK細胞が発現するIL2レセプターに結合し,増殖や活性化を促進させます。
このような方法で,T細胞を安定して大量増殖させることが可能なため,現在行われている免疫細胞療法の中では,最も普及している方法です。
このような方法で獲得できる免疫細胞はほとんどがT細胞の一種であるαβT細胞であり,その他NK細胞,γδT細胞も少量存在します。
αβT細胞療法は,免疫細胞療法の中では,古くから行われている治療法でもあるため,実績が豊富であり,その安全性について確立している治療法といえます。
培養が比較的容易なため,採血に必要な血液量も少なくてすみ,培養期間も短いという長所があります。
がんが進行していたり,抗がん剤治療等のために血液中のリンパ球の数や機能が低下している場合でも,十分な量まで増殖が可能なケースが多いことも特徴といえるでしょう。
ただし,この治療法の問題点は,T細胞が活性化されても,このT細胞はがんの特徴を知らないため,直接がんを攻撃しないということです。
このT細胞ががんを攻撃できるようになるためには,がんの抗原を認識する必要があるのです。
この活性化されたT細胞が体内で樹状細胞などから,どれだけ抗原提示を受け,がん抗原を認識するのかは,はっきりとわかりません。
つまり,いくらT細胞を増加させたところで,がん抗原を認識していないT細胞は,役に立たないのです。
これが,このαβT細胞の限界ともいえるでしょう。
事実,この治療法単独での,がん細胞への傷害活性度は,がんの抗原を認識させたT細胞によるCTL療法よりは弱いといえます。
国立がんセンターの報告では,肝臓がんの手術の後に,補助療法としておこなったところ,再発率が有意に減少したという報告があります。
この治療法単独で,臨床試験第Ⅲ相をクリアしたものはなく,やはり手術や放射線,抗がん剤,との併用療法で効果を上げているようです。
たとえば,海外の試験例では,脳転移をともなう悪性黒色腫患者に対する,放射線・抗がん剤治療後の活性化リンパ球併用療法において26名の患者中,9名が脳腫瘍が完全消失したか,部分縮小したと報告されています。
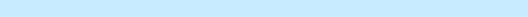 |
|
|
|